学校の授業でアクティブ・ラーニングを取り入れた授業をちゃんと実践していますか?

アクティブラーニングやっといてって生徒に言ってます!

え、アホなん?え、アホなん?
新しい教育方法として注目が集まっているアクティブ・ラーニングですが具体的にはどんな教育方法なのでしょうか。
ということで、今回はアクティブ・ラーニングについて実際の手法や問題点をご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
・ひよっこのみなさま
・アクティブ・ラーニング実践したい
アクティブ・ラーニングとは?

アクティブ・ラーニングとは、生徒が主体的に学習に参加する学習方法のひとつです。
これまでの授業は、「先生が教え、生徒が聞く」という一方通行の学び方であったため、生徒が受け身になってしまいがちでした。
それに対し、アクティブ・ラーニングでは、グループディスカッションやディベートといった先生と生徒の双方向のコミュニケーションを通じて、生徒が主体となって課題の解決に取り組むのが特徴です。
アクティブ・ラーニングは、早くから大学の授業で取り入れられていました。
2014年11月の文部科学省中央教育審議会で、小中高の学習指導要領の見直しの際にアクティブ・ラーニングが言及されたのを機に、大学生だけでなく小中高でも積極的にアクティブ・ラーニングが取り入れられるようになっています。
アクティブ・ラーニングの普及により、これからの時代に求められる自ら学ぶ力が養われることが期待されています。
アクティブ・ラーニングの実際の手法

アクティブ・ラーニングには、いくつかの手法があり、学習のねらいや参加人数、時間などに応じて、どのような手法がよいか選択していくことになります。
Think-Pair-Share(シンクーペアーシェア)
ほかの人との会話を通じて、自分の考えを明確にしていく手法です。
2人1組のペアとなり意見の交換をしたり、それぞれのペアで話し合った内容を共有したりします。
ラウンド・ロビン
5名程度の人が集まってグループとなり、順番に意見やアイデアを話していく手法です。
あらかじめ記録者や制限時間を決めておき、テーマや質問に対して順番に発言していくことで、新しい考えを生み出していきます。
ピア・レスポンス
書き手と読み手、両方の視点を体験することで表現能力を高める手法です。
具体的には、レポートやプレゼンテーションなどの企画の概要(アウトライン)について、話す・聞くといった役割を交代でおこないます。
上記のほかにも、ジグソー、マイクロ・ディベート、LTD(Learning Through Discussion:ラーニングースルーーディスカッション)といった手法があります。
※より詳しく知りたい方は、下記を参考にしていただければと思います。
参考:長崎大学教育開発推進機構
アクティブ・ラーニングの現状の問題点

これからの時代を担う人材を育成するという意味で、大きな期待が寄せられているアクティブ・ラーニングですが、現状の問題点としては、どのようなことがあげられるのでしょうか。
手法の選択がむずかしい
アクティブ・ラーニングには様々な手法がありますが、それらの手法を選択する明確な基準が存在するわけではありません。
そのため、どのような手法に取り組むか選択がむずかしいという問題点があります。
成績評価が従来と違う
正解を導くことに重きが置かれた従来の学習に対し、主体的に学ぶことを重視するアクティブ・ラーニングでは、成績評価が従来と違うという点も問題のひとつです。
人に依存する
1対多で先生が生徒に教える従来型の授業と、アクティブ・ラーニングとでは、先生の役割も変わってきます。
グループワークで生徒間の積極的な意見交換を促すファシリテーションや、議論が白熱し過ぎてしまった場合のトラブル対処など、先生や生徒の姿勢や言動に学習の成果が左右されるおそれがあります。
アクティブ・ラーニングは様々な教育現場で実践されており、その経験がこのような問題の解決へとつながっていくはずです。
しかし、現状では先生の判断にゆだねられている部分が多い点に留意しましょう。
まとめ
以上で、アクティブ・ラーニングをご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

アクティブ・ラーニング、ぜひチャレンジしていきたいですね!

学ぶ楽しさが身につく、これが一番ということ!
アクティブ・ラーニングの取り組みにより、これからの時代を担う人材育成の可能性が広がりつつあります。
今後も動向をウォッチしていきましょう。

にほんブログ村のランキングに参加しています!
こちらからひよっこ教員向上委員会の順位が確認できますのでご興味があればぜひクリックしてみてください!





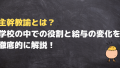
コメント